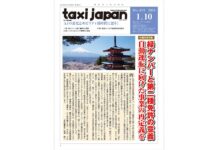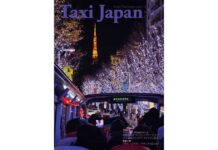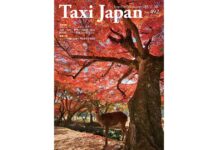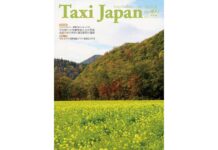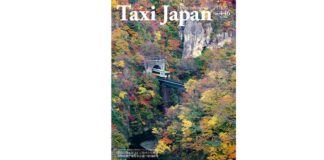東京都特別区・武三交通圏では、新型コロナ禍の中で高齢者を中心に多くの乗務員が退出したが、その減少傾向が止まらず、タクシー需要が集中する時間帯や場所におけるタクシー不足が社会問題を惹起しかねない状況となっているが、東京タクシーセンターによる法人タクシー乗務員への運転者証発行件数の推移をみると、ようやく下げ止まりと回復の兆しが垣間見える。
タクシー運転者の確保が難しいとみなされてきた要因の一つが、他産業との賃金格差の拡大だが、昨秋の運賃改定以降における東京都特別区・武三交通圏の状況は、必ずしもそうとはいえない。東京ハイヤー・タクシー協会がまとめた直近のタクシー輸送実績によると、特別区・武三地区における3月分の全事業者実績は、年度末ということもあり実働日車営収が6万2726円となった。
全事業者平均の実働日車営収が6万円を超えるという数値をどう見るか。3月分6万2726円で月間12乗務をすると月間営収は75万2712円となる。単純に賃率60%として45万1627円となる。この数字は、あくまで平均値であり、個別には、「自社の乗務員の平均給与が50万円を超えている」と話す経営者もいるが、それが特別なタクシー会社における特殊事例ということではなく、むしろスタンダードといえる。
乗務員不足による実働率の低下が、皮肉にも需給調整機能を果たし、実働日車当たりの営収増加をもたらしたもので、その結果として乗務員の賃金が大幅にアップしたといえる。そのことによって、「タクシーは稼げる」との情報が拡散されているのだろう。対前月比で僅か277件という運転者証の発行数増とはいえ、この傾向を維持、拡大していけば、需要対応に必要な乗務員数の確保も可能ではないか。
実働日車営収が新型コロナ禍前を大幅に上回っているが、その反面、総営収は下回ったままである。この状況で乗務員の確保が進めば、現在のような高営収=高賃金が下がりかねない。そうならないように、東京業界として、現在の営収=賃金の水準を維持しながらの乗務員確保策に知恵を絞ってもらいたい。
(高橋正信)
次回Taxi Japan 436号 をお楽しみに!

Taxi Japan最新号は公式サイトでご覧いただけます。
日本タクシー新聞社の発行する、タクシー専門情報誌「タクシージャパン」は毎月10・25日発行。業界の人が本当に求めている価値ある情報をお届けするおもしろくてちょっとユニークな専門紙です。
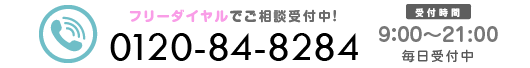








![[2026年2月福岡] トマト交通・会社説明会開催日程のお知らせ トマトタクシー](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2019/05/thumb_tomato-meeting-218x150.jpg)
![[2026年1月] ジャパンプレミアム東京・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/ジャパンプレミアム東京04-218x150.jpg)
![[2026年1月] Z Mobility・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/Z_recruit04-218x150.jpg)