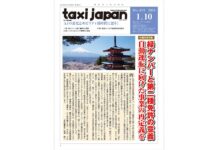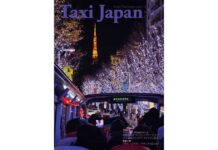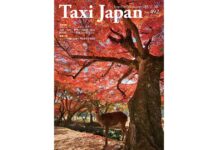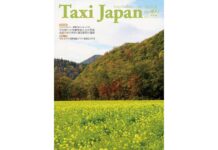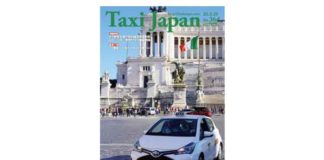タクシー運賃改定申請が全国各地で散見される中で、7月3日には東京都特別区・武三地区においても事業者からの申請が開始された。そして、ほぼ2週間後の7月18日までに、審査開始に必要な法人タクシーの台数ベース5割を超える申請数を早々とクリアしている。その一因は、先に審査開始に必要な申請台数基準が7割から5割に下方修正されたことによるものだが、筆者は、この審査開始に必要な申請割合の台数ベース設定そのものに、かねてより違和感を抱き続けてきた。
その理由は、次による。
まず、タクシー運賃改定申請については、独占禁止法によって、「申請をする、しない」の判断から、初乗り額等の申請内容や改定増収率の設定等々、タクシー事業者間で談合、申し合わせすることを禁止している。そのため、タクシー運賃は個別申請方式を採用していることは周知の事実である。
そんな中で、運輸当局自らがタクシー運賃改定申請に対する改定の要否判定と審査開始を、法人タクシーの台数ベースで5割を超えた段階で着手すると決めているのである。いわば、最低でも台数ベースで5割を超える事業者がタクシー運賃改定に対する考え方や方針について、暗黙のうちに一定のコンセンサスを得なければならない次第を前提としているわけだ。
そして、申請の有無以外の申請内容や改定率についても、独禁法の番人である公正取引委員会の目を気にしながら、事業者間での水面下で事実上の”談合“である「阿吽の呼吸」によって意志統一しているのが実際であり、運輸当局もそれを承知の上で、黙認ではなく前提として審査着手基準を設定しているイレギュラーな成り行きである。
同時に運輸当局は、タクシー運賃を総括原価方式(供給原価に適正な利潤を上乗せした算定方式)で上限運賃を設定し、一定の幅は設定されているものの、事実上の”同一地域同一運賃“の基本方針を定めている。その現状に鑑み、申請当事者のタクシー事業者のみに独禁法を適用することに無理があるのではないか。個別申請方式で申請事業者がそれこそ、思い思いの改定率で初乗り距離や運賃額もすべてバラバラということになれば、運輸当局が審査に当たって戸惑い、混乱が避けられないのは火を見るより明らかだからだ。
特定の条件下で独禁法の適用を除外する特例法が令和2(2020)年11月27日に施行されて、既に一部の路バス事業者による共同経営という形で適用されている。そもそも運輸当局が、実質的な同一地域同一運賃の行政方針を維持するというなら、事業者間のコンセンサス作りを前提とした審査手続き開始の申請台数割合設定をやめて、タクシーの運賃改定に関しては国交大臣の認可を得る手続きを経て独禁法の適用から除外することが本筋ではないか。形骸化した基準を改めるにはばかることなかれ!
(高橋 正信)
次回Taxi Japan 486号 をお楽しみに!

Taxi Japan最新号は公式サイトでご覧いただけます。
日本タクシー新聞社の発行する、タクシー専門情報誌「タクシージャパン」は毎月10・25日発行。業界の人が本当に求めている価値ある情報をお届けするおもしろくてちょっとユニークな専門紙です。
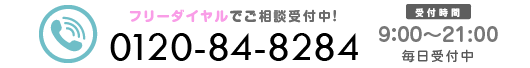








![[2026年2月] ジャパンプレミアム東京・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/ジャパンプレミアム東京04-218x150.jpg)
![[2026年2月] Z Mobility・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/Z_recruit04-218x150.jpg)
![[2026年2月福岡] トマト交通・会社説明会開催日程のお知らせ トマトタクシー](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2019/05/thumb_tomato-meeting-218x150.jpg)