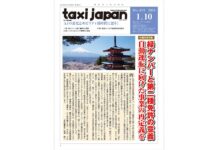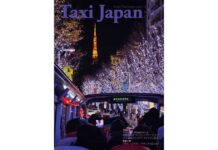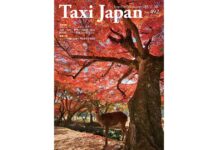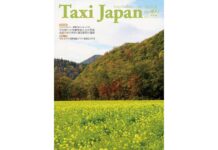自民党の高市早苗・衆議院議員は、先の同党総裁選挙において有力視されていた小泉進次郎・衆議院議員を決選投票で破り、当選した。近く召集される国会で内閣総理大臣に指名され、歴代初の女性首班内閣誕生か、公明党の連立離脱で不透明感が浮上している。ライドシェア解禁反対の姿勢で、これまで自民党内の解禁勢力を連立与党・政府内で抑えていた公明党が連立離脱するという結果になったとはいえ、タクシー業界としては、ライドシェア解禁に積極的な姿勢を取らずに来た高市氏を支持しており、ライドシェア解禁派の小泉氏に競り勝ってホッと胸をなでおろしている構図であろう。
岸田内閣当時のライドシェア全面解禁前夜を思わせる喧噪を振り返るに、すでにライドシェ問題は過去の遺物なのかもしれないが、そうだとしてもタカを括ってはならない。それは、ライドシェア解禁派に対するタクシー業界の主張が、タクシー事業の利益擁護論とみなされ一般世論の賛同を得てきたとは到底思えないからである。
政治体制の変化によってライドシェア解禁論が後退したからといって、タクシー業界は、安閑としていてはならない。政治体制の逆戻を警戒するのではなく、むしろ移動の足を確保する手段としてライドシェア(=自家用車や一種免許運転者の活用)の持つ特異な存在感を、予断と偏見を排除して着目するなど、タクシー業界自らが、移動の足のツールたり得る手段として、現行の日本版の改革も含めてライドシェアと向き合うことを求めたい。
つまり我が国の近未来は、少子高齢化の進展と大幅な人口減少に見舞われることから、国民の移動の自由確保が困難になってくることが容易に想像できるからである。大都市や地方都市、さらに過疎地域などそれぞれの地域事情に即した具体的な移動の足の確保策が講じられなければ、極端な話、過疎地は原野に帰し、地方都市はゴーストタウン化しかねないといえまいか。
この際、国土交通省などの公的な検証とは別に、タクシー業界独自に調査、研究に取り組むシンクタンク的な組織を設置してみてはいかがであろうか。過疎地が原野になるのをライドシェアが食い止めてくれるかもしれないし、自動運転車両は、従来の道路運送法上の旅客運送事業の枠組みを陳腐化する可能性をはらむ中で、多くの移動の足を担う可能性を秘めている。
100年以上の長きにわたって移動のラストワンマイルを担ってきたタクシー業界であるが、シェアリングエコノミーの進展と自動運転技術の進化によって、大いに変化すべき岐路に立たされているのは間違いない。従来の手法や既成概念で測れない時代が、すでにそこまで来ていることを認識しなければならない。
(高橋 正信)
次回Taxi Japan 490号 をお楽しみに!

Taxi Japan最新号は公式サイトでご覧いただけます。
日本タクシー新聞社の発行する、タクシー専門情報誌「タクシージャパン」は毎月10・25日発行。業界の人が本当に求めている価値ある情報をお届けするおもしろくてちょっとユニークな専門紙です。
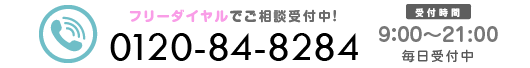








![[2026年2月] ジャパンプレミアム東京・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/ジャパンプレミアム東京04-218x150.jpg)
![[2026年2月] Z Mobility・会社説明会開催日程のお知らせ](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2022/01/Z_recruit04-218x150.jpg)
![[2026年2月福岡] トマト交通・会社説明会開催日程のお知らせ トマトタクシー](https://xn--u9j791glgak65utqb.jp/wp-content/uploads/2019/05/thumb_tomato-meeting-218x150.jpg)